生徒が自ら問いを立てるために必要なこととは?ー個人探究のテーマを見つけるための仕掛けを解説!ー
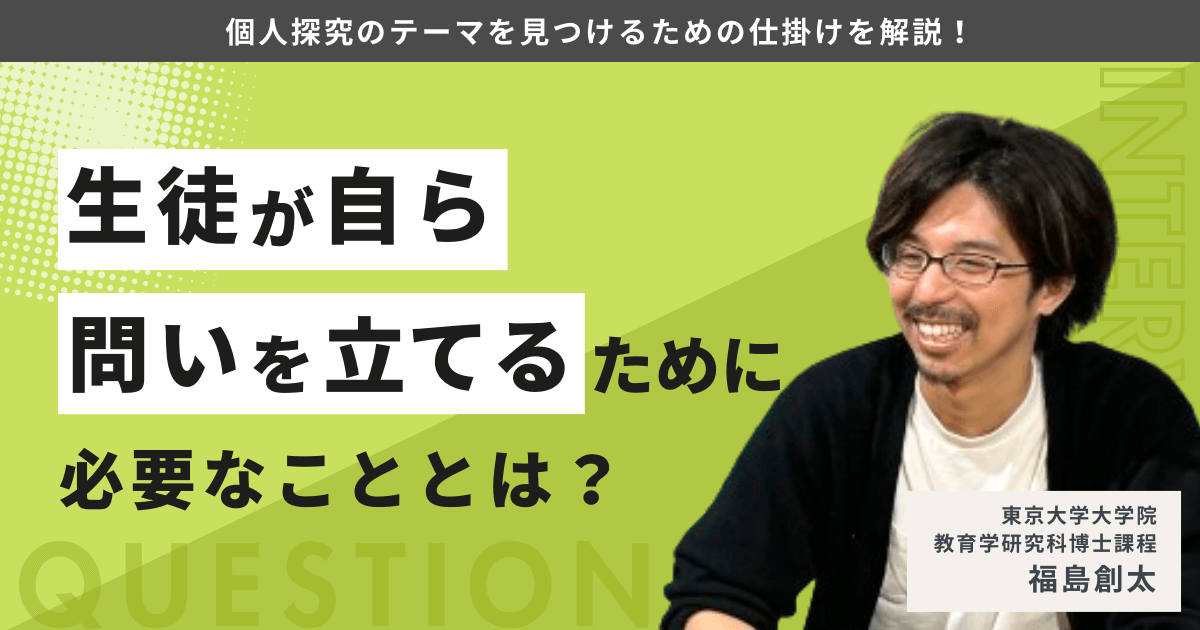
「生徒に個人探究のテーマを決めてほしいけど、なかなか決められない」
「生徒に自分にとって関心ある問いを作ってほしいけど、むずかしいんだろうか…」
生徒に自分の興味があることを探究してほしいと思うけれど、生徒がなかなか自分のテーマをみつけられない。フィールドワークや修学旅行で多くのものに触れる機会を作ってみてはいるけれど、思ったほど深い関心を持ってもらえない。
生徒が自ら好奇心を持ち、ついつい探究したくなる「問い」をつくるには、いったいどうしたらよいのでしょうか?
今回は、「問い」をテーマとした探究学習プログラム「マイクエスチョン」を開発した、教育と探求社開発部マネージャー/ 東京大学大学院教育学研究科博士課程 福島創太さんに、生徒が自ら問いを立てられるようになるために必要なことをうかがいました!
生徒が自ら問いを立てられるようになるには?
ー探究学習では「問い」は欠かせませんが、生徒はどのようにしたら自ら問いを立てられるようになるのでしょう?
そもそも問いを作るのって難しいですよね。
よくある誤解は、「色々な世界に触れたらきっと生徒は勝手に良い問いを立てられるようになるはず」というものです。
例えば、働いている大人たちに出会わせたり、修学旅行やフィールドワークでさまざまな場所に連れていっても、なかなか生徒たちから「問い」が出てこない、という話をよくうかがいます。
もちろん「さまざまな人や場所に出会う」という体験は生徒たちにとって刺激的で大切な体験です。しかし、それだけで生徒たちに高い興味関心が生まれ、「問い」が生まれるかというと、決してそうではありません。
ー思っている以上に、「問いをたてる」のは難しいことなのですね。
そうですね、子どもたちが自ら問いを持つことは、みなさんが思っている以上に難しいことかもしれません。
現代では、子どもたちに限らず、人々は思考停止に陥りがちです。今は皆がスマホを片手に持ち、スワイプすれば新しい情報や面白いコンテンツにすぐに出会えます。
簡単に没頭できるスマホの世界から、顔をあげて自分の周りの世界をみる、そして「なんでこうなってるのだろう」と興味関心を持って考えることは、難しい。インターネットで調べて結果が出てくるような「情報収集的な問い」を持つことはできても、自らの興味関心から生まれる「なぜ?」を考える「探究的な問い」が出てきづらいのはこのためです。
ーそれでは、いったいどうしたら生徒たちが「問い」をたてられるようになるのでしょうか?
私は、まずはじめに「問いを持つのが面白い!」という体験をすることが重要だと考えています。
「興味を持とう、問いを持とう」と意志に働きかけるより、「問いの面白さ」を体験させること。
考えたり、興味をもったり、違和感を感じたり、「なんでなんだろう?」と疑問を持ったり。問いを持って世界に関わることの面白さを知れば、生徒たちは日常的に「問い」を持ちはじめ、対象や世界への関心も広がっていきます。
「問いを立てるのが面白い!」生徒の気持ちが動く仕掛けとは?
ーそれでは実際どのようにしたら、生徒たちに「問いを持つのが面白い!」と思ってもらえるのでしょうか?
まずは、「問い」に強制的に出会わせることです。
はじめから「問いを持ってみよう」といっても、慣れてなければ問いそのものが浮かばない。いきなりゼロから問いをつくるのは、大人でも難しいのではないでしょうか。
そこで、自ら「問い」を生み出そうとするのではなく、まずは「問い」に出会わせてみるのです。
例えば、探究学習プログラム「マイクエスチョン」では、まずは生徒たちが自然と、楽しみながら、たくさんの「問い」に出会えるような設計を行っています。
ー「問い」に出会える設計とは、どのようなものですか?
カードゲームの形式で、どんどん「問い」を作って、どんどん「答え」を考えていきます。面白かった「問い」や「答え」に生徒同士でポイントをつけ、獲得したポイントで勝敗を決めます。
勝ち負けがあるゲームの形をとることで生徒の「やりたい」気持ちが駆動しますし、ゼロから問いを考えなくても、カードがあるのでたくさんの問いに触れることができます。
カードを使った問いの作り方は簡単で、「問いカード」と「テーマカード」の2種類を組み合わせるだけ。
カードを組み合わせると、例えば
「自信の”量”が増えれば増えるほど、減るものは?」
「”力”はなぜ美しい?」
「使い終わった”星”の使い道は?」
といった問いができます。
これらの問いには答えがありません。だからこそ、人によって異なる面白い答えがでてきます。「そんなふうに考えたのか!」と教室が盛り上がり、人との違いを楽しみながら、たくさんの問いに触れることができます。そして、いろんなことを考えたり意見を言い合ったりした起点にあった「問い」に改めて意識を向けることで、問いの魅力や可能性を体感してもらいます。
個人探究のテーマにつながる、生徒自らの問いを見つけるには?
ーそうしてたくさんの「問い」に出会うことで、個人探究にもつながりうる自分ならではの「問い」をみつけることにつながるのですね。
そうですね。問いの魅力を体感したり、日常的に問いを持ちながら世界に関わる中で「個人探究につながる問い」も芽生えやすくなったり、自ら考えられるようになっていくと思います。ただ、「自らの問い」や「個人探究のテーマ」を見つけようとする前に、少し意識しておいてもらいたいことがあります。
それは、「問いは主観的な関心の表れである」ということです。
今の時代、SNSも発達し、多くの人が客観的指標に毒されています。「周りにどう思われるか」「これを言って大丈夫だろうか」ということに中高生の生徒たちも気を配っており、本音を言わずに「なんとなくそれっぽいことでやりすごそう」「誰からも批判されなそうなことを言っておこう」とリスクを回避していることも多いです。
問いには「自分はどう思うのか」「なにに興味があるのか」といった主観が含まれます。それを語って「そんなこと考えてどうするの?」「意味ないじゃん」と言われたら、誰だって傷つきますよね。本当に関心がある問いほど、それを表現して扱っていくのはハードルが高いことなんです。
こうした中高生のおかれている状況や繊細さについても、考慮しながらプログラムは設計しています。例えばさきほどのようにカードゲームで問いを作れば、問いは「カードを組み合わせてできた」だけなので、「これに関心があります」と自分をさらけださなくてもいいですよね。
ーこうした状況から、どのように個人探究につなげていけばよいでしょうか。
そのためには、やはり問いに触れて、問いを楽しんでもらうことです。
「マイクエスチョン」のプログラムの後半では、「問いカード」の中から好きな問いを選び、その問いを持って日常を過ごします。
例えば、「使い終わった〇〇の使い道は?」を選んだら、「〇〇」に「うわばき」「文化祭の装飾」「返却されたテスト」など、日常のものをあてはめていきます。
すると、いつもの通学路や教室がなにか違って見えてくる。問いをとおして世界をみることで、世界がもっと面白くなるように感じていきます。
また、問いから問いが生まれていく体験もあります。例えば、「使い終わった”うわばき”の使い道は?」→「リサイクルに出す」→「できないところもあるんだ、なんでだろう?」「どうしたら使えるんだろう?」といったように、問いがどんどん派生していく面白さもあるでしょう。
そして、いつの間にか「問い」を持つようになり、個人探究のテーマになるような、自分の興味関心にそった「問い」が生まれてくるかもしれません。
自分の主観をさらすこわさについても、「こんなに面白い問いだったら、自分の好きなものあつかえるかもしれない!」「誰かのジャッジにさらされてもやってみたい!」と思えるほど、問いを楽しんでもらうことが理想です。
世界に関心を持つ楽しさを感じよう!
ー最後に、メッセージをお願いします。
世界に関心を持ってほしい!
多くの生徒が、考えたり、興味をもったり、違和感を感じたり。「なんでなんだろう?」という問いを日常的に感じ続けてもらえたら嬉しいです。
自分がそのように生きてきて楽しいからということもありエゴなのかもしれませんが(笑)、正解がない今の時代では、世の中にある成功法や自分の中にあるこだわりに執着していては物事を解決できません。自らの「問い」を持つこと、内省して新しいことを試していくマインドを持つことは、この時代を生きていくために大事なことです。そして何より、生きるのが面白くなります。
世の中には格差の問題も根強くありますが、どんな環境に置かれたとしても、「自分で考える歓び」を知っていたら、きっと生きるに足ると感じられる瞬間が増えるんじゃないかと、信じています。
私は、すべての子どもたちに自ら考え、そして生きることを楽しんでほしい。そして「問い」を持って世界と関わることで、そのことが実現できると信じています。
教科書で知識を得るのではなく、世界の捉え方を知り、自分の価値観・世界観にゆらぎを起こすことが探究学習のすばらしさです。
これまでの「スキルや知識を増やす垂直的な学び」だけではなく、「常識や当たり前が拡張していく水平的な学び」を、先生方とともに作っていけたらと思います。
ーありがとうございました!


この記事へのコメントはありません。